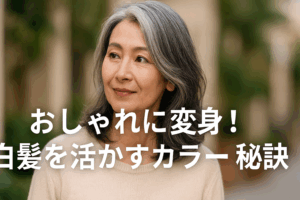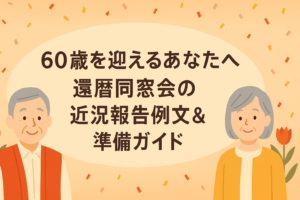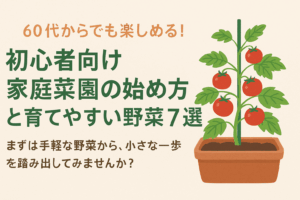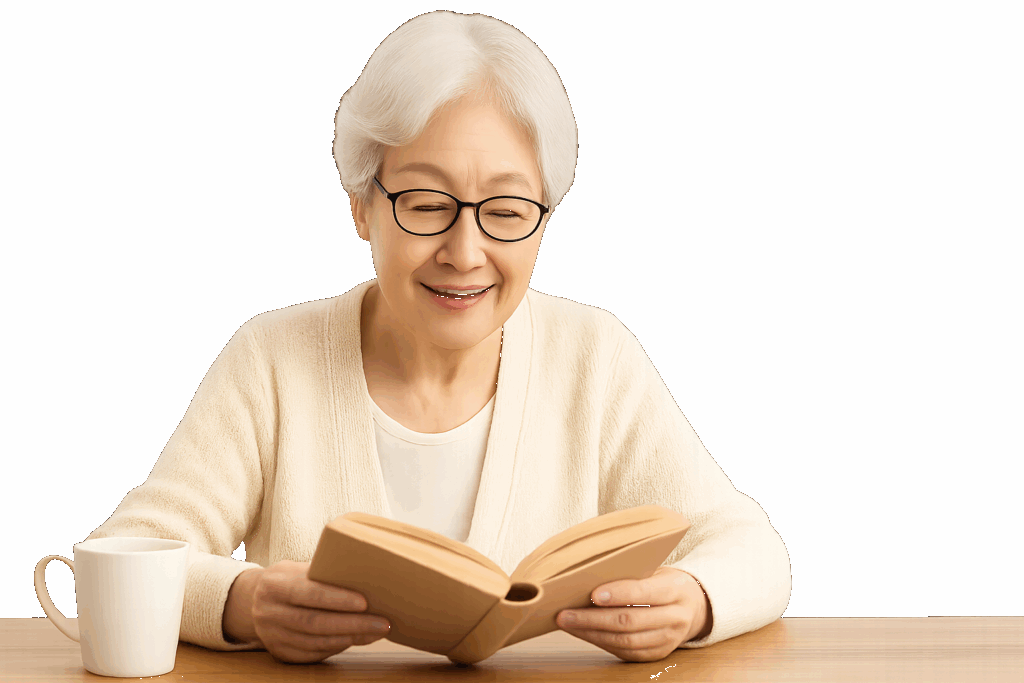
60代は、子育てや仕事が一段落し、自分のための時間が増える大切な時期です。そんな時こそ、読書という静かな習慣が心の栄養になります。本のページをめくるたびに、知らなかった世界や感情に触れ、日々の暮らしに深みが増していきます。
この記事では、人生経験を積んだ60代の方が「本当に出会ってよかった」と感じられるような、おすすめの本をジャンル別に10冊ご紹介します。心を癒やし、勇気づけてくれる一冊を、ぜひ見つけてください。
心を整えるエッセイ・随筆
『日日是好日』(にちにちこれこうじつ) 森下典子
お茶の稽古を通して日常を味わい尽くすことの大切さを教えてくれる一冊。静かな文章に、心がすっと落ち着きます。
著者が20年以上通い続けた茶道教室での日々を綴ったエッセイで、季節ごとに移ろう自然の風景や、茶道の所作に込められた意味、美しさが丁寧に描かれています。「よくわからないまま続けてみること」や「五感で味わうこと」の大切さが語られ、読み進めるうちに、自分の生活にも静かな変化が訪れる感覚を味わえます。
年齢を重ねた今だからこそ、何気ない日常の豊かさや、立ち止まって味わう時間の大切さが、心にじんわりと染みわたります。お茶の稽古を通して日常を味わい尽くすことの大切さを教えてくれる一冊。静かな文章に、心がすっと落ち着きます。
※「日々是好日」とは禅の言葉で毎日が素晴らしい日であるという意味です。
『ツバキ文具店』 小川糸
手紙代筆を生業にする女性の物語。文字に託す思いが、人と人との絆を温かく描き出します。
舞台は鎌倉。鶴岡八幡宮に由比ヶ浜、裏通りの小さな店々──読んでいるとまるで散策しているような気持ちになります。
本を閉じたあと、「手紙を書きたくなる」「誰かへの想いを言葉にしてみたい」と感じる読者が多いのが特徴です。また、手紙を通じた“誰かと繋がる感じ”が、家族や友人へ感謝の気持ちを言葉で伝えたくなる小さなきっかけになると評されています。
静かでありながら心を癒す一冊。
2. 第二の人生に寄り添う小説
『すぐ死ぬんだから』 内館牧子
老いを前向きに、時にユーモラスに描いた作品。共感と笑い、そして生きるヒントが詰まっています。
内館牧子さんらしい“毒舌”とストレートな言葉が随所にちりばめられ、読んでいてスカッとする爽快感があります。登場人物への辛辣な一言も、読者のストレス発散にピッタリです。
『すぐ死ぬんだから』は、60代・70代の方だけでなく、幅広い年齢層に「今をどう生きるか」を考えさせる一冊です。主人公の言葉や行動には強く惹きつけられ、笑い、そして胸が熱くなります。
『長いお別れ』 中島京子
認知症をテーマにしながらも、家族の愛と絆に心が揺さぶられる感動作。
著者自身が認知症を患った父親を10年間介護した経験が下地にあり、実体験をもとにリアルで温かい視点が染み渡っています 。
『長いお別れ』は、認知症に対する不安や節目を感じる60代・70代の方にとって、心暖まるガイドのような一冊です。淡々と過ぎていく日々の中に、愛と向き合う力が息づいていることを教えてくれます。
3. 歴史や知識を深める本
『老いの才覚』 曽野綾子
年を重ねることの意味や知恵を、率直に語るエッセイ。自分の生き方を見直すきっかけになります。超高齢社会を迎えた現代に、自立し豊かに生き抜くための「老いる力」を具体的に提言した一冊です。
『老いの才覚』は60代を迎える今、自分の“これから”を前向きに見つめ、日々を自尊と覚悟を持って生きるための羅針盤のような一冊です。深い学びと共に、自分への問いかけをくれる作品としておすすめします。
『サピエンス全史』 ユヴァル・ノア・ハラリ
人類の歴史をユニークに語る世界的ベストセラー。読後に広がる視野に驚かされます。
本書は単なる過去の解説にとどまらず、「21世紀」「科学技術」「ビッグデータ」への問いかけや、人類が今後どうなるかの思索へと誘います 。
特に、人工知能や遺伝子工学といった「人類を超える存在」への暗示が、現代社会に生きる私たちにも新たな視点を提供します 。
『サピエンス全史』は60代の知的好奇心を満たしつつ、人生を振り返り、これからの生き方を考えるためのヒントが詰まった一冊です。
趣味や暮らしを豊かにする実用書
『暮しの手帖』編集部 編
日々の生活を丁寧に楽しむための知恵が詰まった雑誌的な一冊。料理、裁縫、片付けなど、すぐに実践できる内容が満載です。
『暮しの手帖』は、60代の読み手にとって、
- 座右の書になる「実用知恵」、
- 暮らしを見つめ直す「デザイン視点」、
- 自分らしい「丁寧な暮らし」の考察誌
として非常に価値ある一冊です。豊かな日常を支えるパートナーとして、定期購読も素敵な選択と言えるでしょう。
『やさしい大人の塗り絵』 河出書房新社
心を整え、集中力も高めてくれる大人の趣味本。読書が苦手な方にもおすすめ。
親しみやすさと上質な趣味体験
- 大きな線と文字で塗りやすい設計
線が太めで、細かすぎず見やすく、初めて塗り絵に挑戦する方でもストレスなく楽しめる構成です。例えば「庭に咲く花編」ではバラや桜草、花水木など親しみある植物が描かれており、穏やかな気持ちで取り組めます 。 - テーマごとのバリエーション
春・夏・秋・冬の花、東北の風景、ディズニーキャラクターなど、風景から動植物まで多彩なモチーフを用意し、飽きずに続けられる点が魅力です 。
品質にこだわった構成
- しっかりした厚手の画用紙
ミシン目で切り離せて、そのまま飾れる上質な素材を使用。鉛筆、色鉛筆、クレヨンいずれにも耐える厚さです 。 - 原画参考例付き
塗りの方向性が分かる見本・原画付き。アレンジを楽しみながらも「美しい完成形」を目指す安心感があります 。
心と身体を整える時間
- 集中力とリラックス効果
丁寧に色を塗る作業はマインドフルネス効果があり、心を落ち着かせ、リズムある暮らしを支えます。 - 達成感がもたらす自信
一作品を完成させるという達成体験が、小さな自信を積み重ね、自己肯定感を高めます。
『やさしい大人の塗り絵』は、ゆったりした時間を楽しみたい60代にぴったりの趣味です。日常に彩りを添える“手作りの癒やし”として、ぜひ生活の一部に取り入れてみてはいかがでしょうか。
自分と向き合うための哲学・人生論
『生きがいについて』 神谷美恵子
医師として多くの患者と向き合ってきた著者が語る、「生きる意味」の深い考察に心打たれます。
本書の背景と構成
- 初版は1966年、精神科医として長年ハンセン病療養所で患者と向き合ってきた神谷美恵子が執筆。
- 全11章構成。「生きがいとは何か」「失ってどう取り戻すか」「精神的な生きがい」など、人生の迷いや痛みに寄り添うテーマが並びます 。
「生きがい」とは何か
- 単なる幸福や快楽とは異なり、「腹の底から湧き上がる喜び」「自我に深く関わる高揚感」を伴うもの。それは「やりたいからやる」行動の中に芽生えます。
- 生きがいを感じる人は他者に対して寛容で、将来への前向きな心の姿勢を持つ、と分析しています 。
苦悩の底から立ち上がる力
- 本書は「人生の底」とも言える極限状態(病気・孤独・死との直面)を経験しても、新たな生きがいを発見しうる人々の姿を描写します 。
- 悲しみを土壌にして、自然や他者とのつながりの中で“新しい光”を見出していく、そのプロセスが深く描かれています 。
60代に響くポイント
- 困難との共存:「生きがいは奪われても、新たに見つけられる」という考え方は、人生の節目を迎えた人に特に励ましになります。
- 深い洞察で心に響く:哲学・文学・病跡学などからの引用も豊富で、思索的で重みある内容が頭と心に響きます 。
- 自他への寛容:「腹の底からの喜び」がもたらす寛容さの描写は、大人の人生観と共鳴しやすいテーマです 。
『生きがいについて』は人生の終盤に向かう60代にとって、「今の自分にまだ『生きがい』はあるのか?」という問いに真っ直ぐ向き合い、心の芯に希望の灯をともしてくれる一冊です。静かで深い読書体験をお望みの方に、とてもおすすめします。
『老いの福袋』 樋口恵子
人生100年時代を前向きに生きるための、知恵とエールが詰まったエッセイ。ユーモアも交えながら、等身大の老いと向き合えます。
著者88歳、リアルでユーモアある「老いの実況中継」
- 樋口恵子さんが88歳の“今”感じる「ヨタヘロ期=老いるショック」を赤裸々に綴ったエッセイ集。駅の和式トイレで立ち上がれなくなる事件など、笑いと驚きが交差する日常のエピソードが満載です。
88個の「ころばぬ先の知恵」
- 「老年よ、大志を抱け、サイフも抱け!」という力強いメッセージとともに、生活・お金・介護・終活など幅広いテーマを88項目にまとめています。まるで年齢を重ねる先輩からの手紙のようです。
ユーモアと希望のバランス
- 病気や生活の衰えをエピソードとともにユーモラスに描写しつつ、必ず改善策や前向きな思考の工夫を盛り込んでいます。例えばトイレ閉じ込め事件も「ただでは起き上がらない」気概に満ちています。
親子読みにも、 次世代との共感も
- 高齢の親や自身のこれからに不安を抱く子世代にも刺さる内容。母と娘のやり取りから見える、互いの想いと葛藤が淡々とリアルに描かれています。
『老いの福袋』は、「年を重ねたからこそ生まれる困難」をユーモアと実践的知恵で包み込み、60代にとっても身近で温かい“先輩との対話”のような一冊です。「こんな風に歳を重ねたい」と思わせてくれる勇気と安心をもたらします。