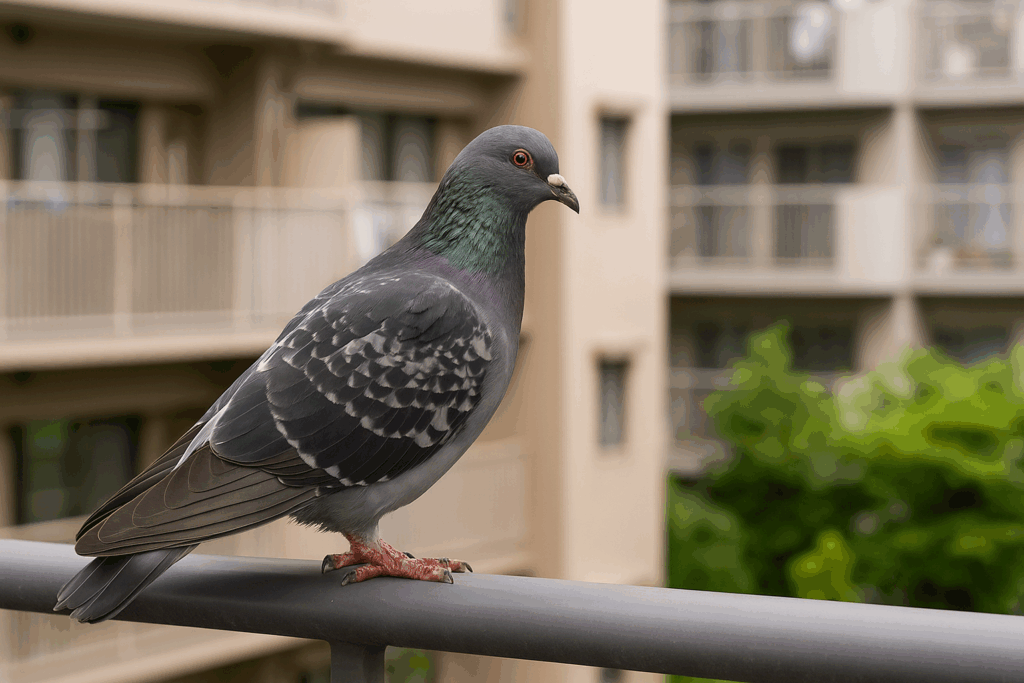
ベランダに鳩が来てしまって、「またフンが落ちている…」「洗濯物が汚れそうで干せない」なんて困ったことはありませんか?
鳩は一度やってくると、また何度も来る習性があり、放っておくとどんどん被害が大きくなってしまうんです。
この記事では、なぜ鳩がベランダに来るのか、そして安心してできる鳩よけ対策を、女性にもわかりやすくまとめました。
さらに、100均アイテムを使った低予算の撃退法や、掃除のコツも紹介しますので、今日からすぐに実践できますよ。
ベランダに鳩が来る理由
鳩の習性が導く「安全・食べ物・休憩所」の三拍子
鳩は安全に休める場所を最優先で探します。次にエサや水があるか、そして長く留まれる居心地をチェックします。ベランダはこの3条件がそろいやすいのです。
安全(見通し+死角)
・高所で天敵が少ない/人の出入りが少ない時間帯がある
・庇(ひさし)や壁で風雨を避けられる
食べ物(におい+土)
・食べこぼし、ペットフード、油染みのにおい
・プランターの土にいる小さな虫や、撒いた肥料・米ぬかなど
休憩所(止まりやすさ)
・手すり、物干し竿、室外機、配管など“止まり木”が豊富
建物の形状と素材がつくる“止まりやすさ”
ベランダの形や素材も、鳩の「止まりやすさ」に直結します。
L字コーナー・庇(ひさし)
・風が巻き込みにくい角や、雨をしのげる庇の下は特に好まれます
手すり・格子・凹凸
・平らで幅広い手すりや、足掛かりのある格子は着地がラク
室外機の熱・配管の陰
・室外機のほんのりした温かさや配管の陰は、休憩スポットになりがち
季節・時間帯・天候で変わる訪問パターン
季節
・春〜初夏/秋は動きが活発(繁殖・エサ探し)
時間帯
・朝夕は巡回、日中は日陰で休憩という流れになりやすい
天候
・雨前後や強風時は、風雨をしのげるベランダに避難しがち
人の生活習慣が“招きやすい環境”に
食べ残し・ゴミ
・ベランダで食べたお菓子のかけら、BBQ後のにおい、調理の油は大きな誘因
プランターまわり
・受け皿の水、腐葉土や肥料のにおい、敷きわらや枝は巣材と誤認されることも
物が多い・布物が多い
・段ボールや家具で死角が増える/ロープやネットに引っ掛かりやすい足場ができる
鳩の“学習”と“なわばり意識”
一度安心すると通い続ける
・鳩は場所記憶が得意。「安全」と覚えると毎日同じルートで来ます
群れへの波及
・1羽が留まる→仲間も真似る→短期間で定着することも
ねぐら・餌場・水場の三角ルート
・ねぐら(高所)→餌場→水場→休憩所の順で回遊し、ベランダがルートに組み込まれると常連化
来訪の“サイン”を見極める
初期サイン
・白い点状のフンが手すりやコーナーにポツポツ
・柔らかい羽毛や小枝・藁が少量落ちている
着地スポット
・同じ手すりに薄い汚れや足跡/室外機の上に丸い汚れ跡
巣作り前兆
・同じ角を何度も下見/朝夕に同じ鳴き声(コォー)が続く
2分でできる“原因特定チェックリスト”
(当てはまる数が多いほど、ベランダが“居心地よく”見えているサインです)
- □ 手すりや物干し竿が平らで幅広い
- □ 室外機の上が空いている
- □ 角や庇の下に風雨を避けられる死角がある
- □ プランターの受け皿に水がたまっている
- □ 食べこぼし・油汚れ・ペットフードの跡がある
- □ 段ボール・家具・物置で隠れ場所が多い
- □ 小枝や藁など巣材らしきものが落ちている
- □ 点状のフンが同じ位置に繰り返し付く
- □ 朝夕に鳴き声が近くから聞こえる
- □ 近隣に公園・神社・高架下など“ねぐら/餌場”になりやすい場所がある
すぐできる軽い環境改善
※本格的な対策は次章で詳しく扱いますが、今日からできる“呼びにくくする工夫”を先に少しだけ。
小さな習慣見直し
・食べこぼしはその場で拭く/受け皿の水は毎回捨てて乾かす
止まり木を減らす
・室外機の上に物を置かない/手すりの平面を覆う工夫(詳細は対策章)
巣材になりやすい物を置かない
・小枝・藁・紐状のものはベランダに放置しない
鳩被害の深刻さとその影響
見た目・衛生面の問題
鳩のフンは見た目の不快感だけでなく、乾くと粉状になって舞いやすくなります。掃除のときは必ず湿らせてから拭き取るのが基本。乾いたまま掃くと広がりやすいので注意しましょう。
生活動線への支障
ベランダに出るたびに靴裏が汚れたり、洗濯物が干しにくくなったり…毎日の小さなストレスが積み重なります。フンで床が滑りやすくなることもあるため、転倒防止の観点でも早めの対処が安心です。
住まいへのダメージ
フンや巣材の放置は、
- 手すり・床材・外壁塗装の劣化につながることがある
- 排水口や溝の詰まりを起こしやすく、雨天時の水はけが悪化
- 室外機のフィンに巣材が絡むと冷暖房効率の低下につながることも
といった住宅面の影響に発展しがちです。
心理的ストレス・睡眠への影響
早朝の鳴き声や羽ばたき音が続くと、睡眠の質が下がる・在宅時も落ち着かないなど、心理面の負担が増えます。「また来たかも…」という不安を減らすためにも、“来にくい環境づくり”の継続が鍵です。
近隣トラブル・管理面のリスク
共用部(手すり外側・外壁・廊下側)まで被害が広がると、ご近所トラブルや管理規約の話題に発展することも。
- まずは写真で記録(日時・場所)
- 管理会社/管理組合に相談(共用部の扱い・許可が必要な対策の確認)
- 個人対策は自宅範囲で安全・静音・景観配慮を意識
が基本の流れです。
二次被害の芽をつぶす
フンや巣材を放置すると、他の害虫や小動物を呼びやすい環境になることがあります。巣材(小枝・藁・羽毛)は見つけたらこまめに回収し、溜めないことが大切です。
子ども・ペットへの配慮
- 触らない・近づかないを徹底(声かけルールを作る)
- ベランダ用サンダルは外置き&定期洗浄
- 掃除後は手洗いの習慣化
といった家庭内ルールを作ると安心です。
季節・天候で変わる“悪化の早さ”
- 春~初夏/秋:繁殖・採餌で活動が活発。定着しやすい
- 梅雨:湿気で汚れが広がりやすい
- 真夏:高温で臭いが強まりやすい
- 雨・強風前後:ベランダが避難場所になりやすい
季節ごとの特徴を意識すると、事前の見回りタイミングが決めやすくなります。
金銭・時間コストの現実
- 日々の拭き取り時間(5~10分でも積み重なる)
- 使い捨て手袋・マスク・シート・消毒液などの消耗品費
- 放置期間が長いほど、クリーニング・補修負担が増えがち
「少しずつの対処」を続けるより、根本対策の一度設置のほうが結果的にコスパが良いケースが多いです。
被害インパクト早見表(軽度→重度)
- 軽度:点状のフンが時々/鳴き声がたまに聞こえる
- 中度:同じ場所に繰り返しフン/手すり・室外機上に汚れ跡/小枝や藁が目立つ
- 重度:巣作りの兆候(材料持ち込み・滞在時間が長い)/排水口詰まり/悪臭や騒音の常態化
すぐ動くべき“サイン”チェック
- □ 同じ角・同じ手すりに何度もフン跡
- □ 小枝・藁・羽毛が増えている
- □ 朝夕の鳴き声が近距離で連日
- □ 排水口の流れが悪い・雨のあとに残水
安全第一の基本ルール(清掃前の準備)
ここは後章で詳しく扱いますが、被害が出ている今すぐ役立つポイントだけ先に。
- 手袋・マスク・使い捨てシートを準備
- 乾いたフンは先に水で湿らせる
- 拭き取り後は密閉して廃棄、最後に手洗い
- 作業後はベランダの風通しを良くする
鳩対策の基本方針
“寄せつけない・居つかせない・戻らせない”の3本柱
鳩対策は、一度追い払って終わりではなく、来させない環境作りがゴールです。次の3つを同時に意識すると、効果が長続きします。
寄せつけない(入口をふさぐ)
- 止まり木を減らす:手すりや室外機の上など、着地しやすい場所を減らす
- 誘因をなくす:食べかす・油汚れ・プランター受け皿の水をこまめにリセット
- 視覚・匂いの牽制:反射テープや匂い系アイテムで“ここは落ち着かない”を演出
居つかせない(快適を奪う)
- 物理バリア:ネット・ワイヤー・トゲ付きシートで“座れない・巣を作れない”状態に
- 死角を減らす:段ボールや家具の山を作らない/巣材になりやすい小枝・紐類は置かない
戻らせない(学習をリセット)
- ローテーション:同じ対策だけだと慣れます。視覚+物理+匂いを季節ごとに組み替える
- 痕跡ゼロ運用:フンや羽毛を残さない。“安心の証拠”を消すことが最重要
対策の進め方ロードマップ(段階式)
今日〜3日:応急処置
- 誘因の掃除・整理(受け皿の水・食べこぼし・油汚れ)
- 着地ポイントの特定(手すり・室外機の上・コーナー)
- 仮置きの牽制(反射テープや動く小物で「落ち着けない」演出)
1週間以内:本設置
- 物理バリアの導入(ネット/ワイヤー/トゲシートのいずれか)
- 視覚+匂いの複合(反射+匂いジェル等)
- 止まり木を構造的に減らす(室外機上を覆う・手すりの平面を活かさない工夫)
1か月以内:定着運用
- 点検と微調整(ズレ・たるみ・剥がれの修正)
- ローテーション表を作る(季節替わりに配置やアイテムを入れ替え)
- 痕跡ゼロ習慣(見つけたらすぐ除去・清掃)
組み合わせ方の基本(レイヤー発想)
- 第一層:視覚 … 気づかせる/落ち着かせない
- 第二層:匂い・感覚 … 居心地を下げる
- 第三層:物理 … 着地・定着を物理的に阻止
→ 少なくとも2層以上を重ねると、慣れ対策&長期化に強いです。
失敗しやすいポイントと回避策
- 見た目だけで置く → 風で動かず効果半減。固定・角度・高さを調整
- 一箇所だけ強化 → 別の場所に着地されやすい。動線全体を面で管理
- 清掃を後回し → “安心のサイン”が残り定着。痕跡ゼロを最優先
- 強すぎる音・光 → 近隣トラブルに。静音・景観配慮で長続き
安全・マナー・ルール(やさしく、ていねいに)
- 安全第一:高所作業は無理をしない/脚立は2人以上で/落下物に注意
- 共用部配慮:マンションは管理規約の確認&管理会社へ相談
- 人と動物にやさしく:傷つける対策はNG。静かで目立たない方法を選ぶ
ベランダ診断チェック(設置前の最終確認)
- □ 着地ポイント(手すり・室外機・角)を特定した
- □ 誘因(食べかす・受け皿の水・油汚れ)を除去した
- □ 視覚+物理の少なくとも2層を準備した
- □ 固定方法(結束バンド/クリップ/粘着)は風対策まで想定した
- □ 近隣・景観・規約への配慮ができている
季節ごとの見直しポイント
- 春/秋:活動活発。物理バリアを強めに、視覚アイテムも追加
- 梅雨:湿気で汚れ拡散。清掃頻度アップ
- 夏:臭いが出やすい。匂い対策+日陰管理
- 冬:風でズレやすい。固定の点検を重点的に
家族と共有したい“3つの約束”
- 置きっぱなしにしない(小枝・紐・段ボール)
- 受け皿の水は毎回捨てる(乾かすまでがワンセット)
- 見つけたら即連絡・即リセット(痕跡ゼロの徹底)
鳩よけ対策の種類
視覚系(光・動き・“ここは落ち着かない”を演出)
キラッと光ったり、ゆらゆら動くものは「安心できない場所」に見せるのに効果的です。
- 反射テープ/ホイル/古いCD
- コツ:手すり・物干し竿・室外機の上に高さ違いで複数設置。風で必ず揺れる位置に。
- 頻度:2週間ごとに場所替え(慣れ対策)。
- モビール・風車・疑似天敵ステッカー(目玉模様など)
- コツ:着地狙いのエッジ(手すりの角・庇の下)に近い位置へ。
- 弱点:単品だと慣れやすいので、匂い・物理と重ね使いが基本。
匂い・感覚系(スプレー・ジェル・顆粒)
不快な匂いやベタつき感で「居心地を下げる」方法。
- ハーブ系・柑橘系・酢酸系の忌避スプレー/ジェル
- コツ:着地線上(手すり天面・室外機の縁・コーナー)に点在配置。
- 注意:雨・直射日光で効果が落ちやすいので、こまめな補充を。換気・小さなお子さんやペットの触れやすさにも配慮。
- 顆粒タイプ
- コツ:コーナー部や溝に薄く帯状に。掃除時は集めて密閉廃棄。
音・超音波系(※近隣・規約に配慮)
- 向き不向きが大きいため、集合住宅では最終候補に。
- 使用可否や時間帯は管理規約やご近所の状況を確認。静音設計でも長時間は避けるのが無難です。
- 代替案:上記の視覚+匂い+物理の重ね使いのほうが安定して続けやすいことが多いです。
物理バリア(“座れない・作れない”をつくる本命)
長期的に安定しやすいのは、実はこの物理系。見た目と安全性に配慮しつつ導入を。
- バードネット(おすすめ)
- 目的:ベランダ全体を面でブロック。
- コツ:メッシュは指が入らない細かさ/たるみNG/四辺を連続固定(結束バンド・クリップ)。
- 注意:避難ハッチ・はしごに被らないよう設計。賃貸は原状回復しやすい固定(養生+クリップ)で。
- ワイヤー(糸)張り
- 目的:着地エッジ(手すり天面)を不安定にする。
- コツ:2本張り(前端と少し内側)で足掛かりを消す。間隔と高さを均一に。
- 注意:透明糸は見えにくい→目印を少し付けると安全。
- 鳥よけマット(スパイク)
- 目的:手すりや室外機の上に“座れない面”を作る。
- コツ:面で敷き詰めて隙間ゼロ。両面テープや面ファスナーで着脱式にすると掃除がラク。
- 注意:鋭すぎるものは避ける(安全第一)。
- 室外機対策
- 室外機上にマット/上面だけでも“座れない”処理。
- 吸気・排気の妨げNG。熱効率を落とさない配置に。
DIY対策(手軽・低コストで“試しやすい”)
- アルミホイル帯×吊り
- 作り方:2〜3cm幅で細長く裂いてひねり、S字フックで垂らす。
- コツ:長さ違いで複数本、角と手すり中心に。
- テグス(透明糸)ライン
- 作り方:手すり上方に水平ラインを2本。
- 注意:見えにくいのでタグを所々に付ける(安全)。
- 園芸ネット+支柱
- 作り方:支柱2〜3本で簡易フレーム→ネットをピンと張る。
- コツ:たるみ対策に結束バンド多め。
100均グッズ活用(ダイソー・セリアで揃う定番)
- 反射テープ/モビール/S字フック/結束バンド
- 園芸ネット/ワイヤーネット/吸盤フック
- 鳥よけマット(柔らかめタイプ)/すき間埋めスポンジ など
組み合わせ例(3パターン) - 手すりタイプ:ワイヤー2本張り+反射テープ→慣れ予防に2週間で配置替え
- 室外機タイプ:鳥よけマット全面+反射モビールを上方に1つ
- 開放ベランダ:園芸ネットで部分囲い+角に反射タッセル+足元は顆粒
ケース別おすすめ(住まいの形と状況で選ぶ)
- 高層階・風が強い:物理バリア中心(ネット・マット)。視覚アイテムは固定優先。
- 低層・近隣に樹木や公園:視覚+匂い+物理の三層。とくにコーナー部の死角に集中配置。
- 子ども・ペットがいる:無臭・低刺激の対策を優先/触れやすい位置のジェルは避ける。
- 賃貸・規約が厳しい:着脱・原状回復がしやすい固定(クリップ・面ファスナー・養生テープ+結束)。
失敗例とリカバリー
- テープだけで終わり → 匂い or 物理と重ね使いに変更。
- 設置はしたが“隙間”がある → エッジとエッジの連続性を意識して面でふさぐ。
- たるみ・ズレ → 風の主風向を想定し、固定点を追加。
- 目立ちすぎて景観が気になる → 色味を建物に合わせる・透明糸+小タグに。
メンテナンス&ローテーション(慣れさせない運用)
- 週1の見回り:ズレ・剥がれ・たるみを即修正。
- 月1の入れ替え:配置・角度・高さを少し変える(“初見”感を維持)。
- 痕跡ゼロ:フン・羽毛・小枝を見つけ次第リセット。安心の証拠を残さない。
迷ったらここから:ミニチェックリスト
- □ 視覚+物理の2層以上になっている
- □ 着地エッジ(手すり天面・室外機縁)を徹底的に処理した
- □ コーナー部・庇下など死角にも何か置いた
- □ 固定点は十分(風で動かない)
- □ 賃貸/避難経路への配慮ができている
- □ 2週間ごとの小変更計画を立てた
ポイント:
“見せる(視覚)× イヤにする(匂い)× できなくする(物理)”のレイヤー重ねが長持ちのコツ。
とくに物理バリアは効果が安定しやすいので、視覚・匂いを添えて“慣れ”を防ぐ運用が安心です。
100均グッズでできる鳩対策
「なるべくお金をかけずに、でも効果的な鳩よけをしたい!」という方にとって、ダイソーやセリアなどの100均グッズは強い味方です。実は、鳩よけ専用アイテムだけでなく、園芸や収納コーナーにある日用品が鳩対策グッズに変身するんです。ここでは、具体的にどんなアイテムが使えるのか、どんな工夫で長持ちさせるかを深堀りしてご紹介します。
ダイソー編:定番アイテムと応用例
- 鳥よけ反射テープ/キラキラモール
- 太陽光や風で揺れると強い反射を放ちます。
- 使い方:ベランダの手すり・物干し竿に垂らして吊るす。
- ポイント:長さ違いで複数本をランダム配置。風で動くたびに「落ち着かない場所」に。
- ワイヤーネット&結束バンド
- もともとは収納用ですが、組み合わせれば簡易バードネットに。
- 使い方:ベランダの柵や室外機周りを覆う。
- メリット:見た目がスッキリ、外からの視線除けにも。
- すき間埋めスポンジ/クッション材
- 鳩は細い足場でもうまく止まります。隙間を埋めるだけでも着地できなくなることも。
- 使い方:手すりの平面や角にスポンジを貼って“足場を不安定”に。
セリア編:工夫しやすいアイテム
- 園芸用ネット(細かめ)
- 鳥よけネットとして使う人も多い人気アイテム。
- 使い方:ベランダの内側や物干しスペースにピンと張る。
- 注意点:たるみがあると入られてしまうので、結束バンドでしっかり固定。
- アルミホイルシート/ホログラムシート
- 太陽光の反射+音で威嚇。
- 使い方:ベランダの壁に貼る/小さく切って吊るす。
- 応用:ガチャガチャカプセルの中に入れて“反射玉”を自作。
- 吸盤フック&S字フック
- ネットや反射テープを吊るすときに便利。
- ポイント:穴あけ不要なので賃貸でも安心。
意外なアイテム活用例
- キッチンアルミホイル
- くしゃくしゃにして吊るすと、光+カサカサ音でダブル効果。
- 風車・モビール
- カラフルに回る姿は子どもが喜ぶと同時に鳩避けにも。
- 人工芝マット
- 手すりや室外機の上に敷くと、鳩にとって“座り心地が悪い”環境に。
組み合わせ術(100均だけで作る鳩よけ3パターン)
パターン1:手すりタイプ
- ワイヤーネットを手すりに固定
- 反射テープをS字フックでぶら下げる
→ 鳩が最も狙う「手すりの着地」を完全ブロック
パターン2:室外機タイプ
- 室外機上に人工芝マット
- 周りに反射モビールを吊るす
→ 「座れない+落ち着かない」でダブル牽制
パターン3:角&コーナー対策
- 園芸ネットでコーナーを囲う
- 内側にアルミ玉や風車を設置
→ 巣作りに選ばれやすいコーナーを“不快ゾーン”に
100均鳩対策のコツと注意点
- 複数併用が基本:1種類だけでは慣れやすい。
- 定期的に入れ替える:2週間~1か月ごとに位置や高さを変更。
- 見た目と安全に配慮:景観や近隣への反射光、強風での飛散に注意。
- 原状回復しやすく:賃貸ならテープよりもフックやクリップで固定を。
まとめ:100均鳩よけの魅力
- コスパ最強:数百円で始められる
- 試行錯誤しやすい:失敗しても痛手が少ない
- DIY感覚で楽しい:自分仕様にカスタマイズ可能
特に「これから対策を始めたい」という初心者さんには、100均アイテムを組み合わせた“お試し鳩対策”がとてもおすすめです。
100均鳩よけアイテムおすすめランキングBEST5
第1位:鳥よけ反射テープ・モビール
✨ キラキラ光る&風で揺れるのが鳩にとって不快!
- ダイソー/セリアの定番商品で種類豊富
- 手すりや物干し竿に吊るすだけで簡単
- 2週間ごとに位置や角度を変えると効果持続
👉 初めての鳩対策に一番おすすめです。
第2位:園芸用ネット(細かめタイプ)
✨ 物理的に侵入させない最強バリア
- ベランダのコーナーや手すり内側にピンと張るだけ
- 巣作りされやすい「角」をガードするのに効果的
- 結束バンドや吸盤フックでしっかり固定すれば賃貸でも安心
👉 巣を作られやすい場所にはぜひ取り入れたい対策です。
第3位:人工芝マット・鳥よけマット
✨ “座りにくい環境”を作るだけで来なくなる
- 室外機の上や手すりに敷くと「止まり木」にならない
- 柔らかめタイプなら安全で扱いやすい
- 見た目もグリーンで自然に馴染みます
👉 鳩に「ここは休めない」と思わせるのがポイント。
第4位:アルミホイル・ホログラムシート
✨ 光と音のダブル効果
- くしゃくしゃに丸めて吊るすと「チラチラ光+カサカサ音」
- ホログラムシートを小さく切ってガチャカプセルに入れると“反射玉”に変身
- 費用はほぼゼロで試せるコスパ抜群アイテム
👉 家にあるものですぐに始められるのが魅力です。
第5位:ワイヤーネット&結束バンド
✨ DIY感覚で囲える・覆える万能素材
- 室外機の周りや手すりに設置して「止まれない場所」を作る
- 複数枚つなげれば簡易ネット代わりにも
- 見た目もスッキリ、収納用として再利用も可能
👉 長期的に使える“賢い100均対策”です。
100均鳩よけの成功ポイント
- 組み合わせることが大事(例:反射テープ+人工芝マット)
- 慣れ対策として1〜2週間ごとに配置や高さを変える
- 安全&景観に配慮(強風で飛ばされないよう固定、隣家に迷惑をかけない)
まとめ
100均アイテムは安くて試しやすく、失敗してもダメージが少ないのが魅力です。
「どれからやればいいかわからない…」という方は、
まずは反射テープ+人工芝マットの組み合わせから始めると効果を実感しやすいですよ。
100均鳩よけアイテム比較表
| アイテム | 効果の持続性 | コスト | 設置難易度 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 反射テープ・モビール | △(2週間〜1か月) | ◎(1〜2個100円) | ◎(吊るすだけ) | 初心者向け/手軽に始められる | 慣れやすい→定期的な配置替え必須 |
| 園芸用ネット | ◎(長期的に効果) | ○(1枚100円〜) | △(固定に少し手間) | 巣作り防止に最強/侵入ゼロにできる | たるみNG/風で外れないよう注意 |
| 人工芝マット・鳥よけマット | ◎(設置中は効果持続) | ○(1枚100〜200円) | ○(敷くだけ) | 室外機・手すり対策に有効/見た目も自然 | サイズに合わせてカットが必要 |
| アルミホイル・ホログラムシート | △(短期〜1か月) | ◎(ほぼ0円〜) | ◎(切って吊るすだけ) | 家にある材料で即実践可/コスパ最強 | 強風時は飛散注意/慣れやすい |
| ワイヤーネット&結束バンド | ◎(半年〜長期) | ○(2〜3枚で数百円) | △(少しDIY感覚) | 室外機囲い・止まり木防止に万能 | 見た目に注意/固定をしっかり |
活用アドバイス
- 即効性重視 → 反射テープ・アルミホイルからスタート
- 長期安定重視 → ネットやマットで“座れない環境”を作る
- おすすめ組み合わせ
- 短期+長期でバランスよく:
反射テープ(動的効果)+人工芝マット(物理効果) - 巣作り防止特化:園芸ネット+ワイヤーネット
- 短期+長期でバランスよく:
100均アイテムは単品では限界もありますが、複数を組み合わせて配置替えをしながら使うと効果が長続きします。
「最初の一歩」は反射テープ+人工芝マット、
「本格対策」には園芸ネット+ワイヤーネットがおすすめです。
マンションでの鳩対策
マンションの場合、戸建てとは違って「共用部分のルール」や「近隣への配慮」が大切になります。自分のベランダだけで完結するつもりでも、鳩は移動範囲が広いため、他の住戸や管理規約への影響を考えた対策が必要です。ここではマンション特有の注意点や具体策を整理しました。
共用スペースでの注意点
- 手すり・外壁・廊下側は「共用部分」に含まれることが多い
- 自分の判断で釘打ち・接着剤・ビス止めはNG
- 管理組合や管理会社に必ず相談してから設置するのが基本
👉 たとえば「ネットを張る」「ワイヤーを固定する」などは許可が必要になることが多いので注意しましょう。
個人でできる鳩対策(ベランダ内限定)
- 吊るす・置くだけの方法
- 反射テープ・モビール・アルミホイル玉を吸盤フックやS字フックで吊るす
- 人工芝マットや鳥よけマットを室外機や手すりの上に敷く
- ネットやワイヤーの“仮設固定”
- 結束バンド・クリップ・養生テープを使って原状回復できる形で固定
- 避難ハッチや非常用通路をふさがないよう配置
- 掃除と痕跡ゼロ化
- フン・羽毛・小枝など「安心のサイン」を残さない
- 週1回の掃除+月1回のメンテで「ここは危険」と覚えさせる
管理組合・管理会社に相談する流れ
- 被害の記録を残す
- 写真・動画で「どの位置に」「どのくらいの頻度で」被害があるかを記録
- 共用部か専有部かを確認
- 手すり外側や外壁は共用部扱いになるケースが多い
- 相談内容を具体的に
- 「室外機上にフンが溜まるのでネットを検討しています」など具体的に伝える
- 推奨される対策を確認
- 管理会社から「業者に依頼してください」と案内される場合もある
業者に依頼する場合のメリット・デメリット
- メリット
- 長期保証が付く場合が多く、再発防止効果が安定
- 高所作業など自分では危険な作業を任せられる
- デメリット
- 数万円単位の費用がかかる
- 賃貸ではオーナーや管理組合の了承が必須
👉 「巣を作られてしまった」「何度も繰り返し被害が出る」場合は業者検討がおすすめです。
やってはいけないNG対策
- 強力な接着剤・有刺金属を使う
→ 危険性が高く、近隣トラブルの原因に - 鳩に直接危害を加える行為
→ 法律で保護されているため違法行為にあたります - 大きな音や強烈な光を常時発生させる機器
→ 鳩より先に人間(隣家)が困ってしまう
マンションで効果的な“複合対策パターン”
- 初期段階(まだ鳩が下見に来ている)
- 反射テープ+アルミ玉で「落ち着かない環境」を演出
- フンが付き始めた段階
- 人工芝マットを手すり・室外機に敷く+視覚系アイテム追加
- 被害がひどく、巣作り兆候あり
- 園芸ネットで角を覆う+管理会社に相談(必要なら業者依頼)
チェックリスト:マンション鳩対策前に確認すべきこと
- □ 設置予定場所は専有部分か共用部分か
- □ 原状回復できる方法で対策できるか
- □ 避難経路・通風・景観を妨げないか
- □ 近隣住戸への影響(反射光・落下物など)はないか
- □ 管理規約の内容を確認したか
💡 まとめ
マンションの鳩対策は、「原状回復できる方法」+「管理規約の確認」+「複数対策の組み合わせ」がカギです。
個人の工夫だけでも十分効果を出せますが、長期化・深刻化した場合は管理会社や業者と連携することが安心につながります。
マンションでの鳩対策まとめ表
| 区分 | できること(個人でOK) | できないこと(注意が必要) | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 専有部分(ベランダ内側) | ・反射テープ・モビールを吊るす ・人工芝マットや鳥よけマットを敷く ・アルミホイル玉・風車など置き型対策 ・園芸ネットを仮設で張る(クリップ・結束バンド使用) | ・強力接着剤で固定 ・壁や床に釘やビス打ち ・大きな音や光を出す機器 | ・原状回復できる方法で行う ・風で飛ばされないよう固定 ・避難ハッチ・排水口をふさがない |
| 共用部分(手すり外側・外壁・廊下側) | ・原則NG(管理会社へ相談必須) | ・勝手にネット・ワイヤー設置 ・塗装や外壁に穴をあける行為 | ・被害の記録(写真・動画)を添えて管理会社に相談するのが第一歩 |
| 管理組合や業者対応が必要な場合 | ・定期清掃を依頼 ・業者によるネット設置 ・鳩対策の共同ルール策定 | ・無許可で大規模な工事や強力なバリア設置 | ・費用は数万円〜のケースあり ・長期保証付きプランなら安心度アップ |
| 家庭内ルール | ・子どもに「触らない」教育 ・ペットを近づけない ・鳩フン清掃時は手袋・マスク必須 | ・素手で掃除 ・乾いたフンを掃く | ・掃除後は痕跡ゼロ習慣が大切 ・共用廊下にフンが落ちた場合も報告を |
ポイント整理
- 個人でできるのは「専有部分内」で原状回復可能な範囲のみ
- 共用部分は必ず管理会社・管理組合に相談
- 清掃と痕跡ゼロ化の習慣で「ここは安心できない場所」と鳩に学習させる
鳩フン掃除とメンテナンス
基本の考え方
鳩フンは乾く前に素早く・静かに・安全に。
粉が舞いやすいので、必ず湿らせてから拭き取り、最後に痕跡ゼロまで仕上げるのがコツです。
準備するもの(最小セット)
- 使い捨て手袋・マスク(できれば不織布)
- キッチンペーパー or 厚手の使い捨てシート
- 霧吹き(真水/薄めた中性洗剤)
- ビニール袋(2重にできる枚数)
- 軽い消毒用(住居用の中性クリーナー、または表示に沿って使える塩素系など)
- 使い捨てブラシ or 古歯ブラシ(溝・端用)
ポイント:衣類は長袖・長ズボン。作業後は手洗い・うがいまででOKです(体調不良時は無理せず)。
手順(標準フロー)
- 養生&換気
近くの洗濯物や小物を退避。窓を少し開けて風通しを確保。 - 事前散水(ミスト)
霧吹きで十分に湿らせる(粉が舞うのを防止)。 - 固形分を回収
濡らしたペーパーで包み、そっと持ち上げて2重袋へ。 - 洗浄拭き
薄めた中性洗剤で外→内に拭き進める(汚れを広げない)。 - 消毒・除菌ケア
表示に沿って使える製品を選び、所定の接触時間を守って拭き取り。
※塩素系は酸性洗剤と混ぜない・金属部や色物は目立たない所で試す。 - すすぎ&乾燥
真水で固く絞った布でふき取り、最後に乾拭き。水気を残さない。 - 後片付け
手袋を裏返して外し、使用物は密閉して廃棄。手洗いで完了。
素材別のコツ
- タイル・コンクリ:ブラシOK。目地に入った汚れは斜め方向に軽く掻き出す→再度ミスト&拭き取り。
- 塗装床・木部:こすりすぎると傷に。湿らせ→浮かせる→優しく拭くが基本。
- 金属(手すり・アルミ):塩素系は短時間で。作業後は真水でしっかり拭き、乾拭きで仕上げ。
- 室外機:上面のみを拭き掃除。吹き出し口・フィンには洗剤をかけない(故障予防)。
厚く固着しているとき(リカバリー)
- 湿布法:濡らしたキッチンペーパーを汚れに密着→5〜10分置く→やさしく拭き上げ。
- 段階洗浄:中性洗剤→すすぎ→必要に応じて表示に沿った消毒→すすぎ→乾拭き。
- 線状の汚れ(手すり縁):端から1方向へ拭き、往復しない。
排水口・サッシ・溝のケア
- 排水口:網や溝に巣材(小枝・羽毛)が詰まりがち。ピンセットやブラシで取り除き、最後に水通しを確認。
- サッシレール:細ブラシで汚れを寄せ集め→ミスト→拭き取り。レールの角は念入りに。
ニオイ・再付着を防ぐひと工夫
- 乾燥が最強:水分はニオイと汚れ残りの原因。しっかり乾かす。
- 片付け&断捨離:段ボール・紐・藁状のものは置かない(巣材と誤認されやすい)。
- 仕上げの“居心地ダウン”:手すり天面に人工芝マット/室外機上に座れない面を作って再訪を減らす。
10分クイック法(忙しい日用)
- 手袋・マスク→ミストで湿らせる
- 濡れペーパーで回収→2重袋
- 中性洗剤でサッと拭く→水拭き→乾拭き
- 手すりだけ消毒表示に沿って軽く拭く→乾拭き
- 使用物は密閉廃棄・手洗い
定期メンテの頻度目安
- 見回り:週1(梅雨・繁殖期は週2)
- 排水口・溝:月1で“水通しチェック”
- 対策グッズ:2週間ごとに位置や角度を少し変える(慣れ防止)
- 季節替わり:固定のゆるみ・たるみ・剥がれを総点検
安全チェック(作業前・作業中)
- □ 高所作業は脚立を安定面に/可能なら2人体制
- □ 風の強い日は無理しない
- □ 乾いたまま掃かない(必ず湿らせる)
- □ 酸性×塩素は絶対に混ぜない・連続使用しない
- □ ペット・お子さんは作業エリアに入れない
よくある悩みと対処
- 拭いても輪ジミが残る:もう一度ミスト→中性洗剤で押し拭き→水拭き→完全乾燥。
- 雨で広がった:雨上がりは早めにミスト&回収。濡れているうちがチャンス。
- また同じ場所に付く:着地エッジの処理不足が原因。手すり天面の“座れない化”を追加。
仕上げは“痕跡ゼロ運用”
フン・羽毛・小枝・足跡が1つも残っていない状態をキープすると、鳩は「ここは安心できない」と覚えます。
掃除(除去)→乾燥→居場所消し(対策の微調整)をセットで回すのが、最短でラクになる近道です。
実際に効果があった鳩撃退法ランキング
はじめに、ランキングは「効果の確実性」「持続性」「安全・景観」「コスト」「設置のしやすさ」の5軸で総合評価しています。単品よりも複数の対策を重ねる(視覚+物理)ほうが長持ちしやすいのがポイントです。
第1位:バードネット(面で“入れない”を作る)
なぜ効く?
ベランダ全体を“面”で遮るため、着地も侵入も物理的に不可能にできます。慣れにくく、長期安定。
向いている環境
・コーナー部での滞在が多い/巣作りの兆候がある/再発を確実に止めたい
設置のコツ
- メッシュは細かめ、たるみゼロ、四辺連続固定(結束バンド・クリップ)
- 避難ハッチ・はしごは塞がない(回避ルートを確保)
- 賃貸は原状回復できる固定(養生+クリップ)で
よくある失敗
- 角だけ浮いて“出入口”ができる/一辺だけの点固定で隙間が生じる
維持の目安
- 週1でたるみ・外れチェック/季節の変わり目に張り直し
第2位:手すりワイヤー(テグス)2本張り
なぜ効く?
鳩の着地ライン(手すり天面)を不安定化。前縁+内側の2本で“足場”を消せます。
向いている環境
・手すりや物干し竿に繰り返し止まる/室外機上はあまり使われていない
設置のコツ
- 高さ違いで2本、等間隔でピンと張る
- 透明糸は見えにくい→小さなタグを所々に付けて安全確保
よくある失敗
- 1本だけで別ラインに着地される/テンション不足でたわむ
維持の目安
- 月1で張りの点検/強風後に再調整
第3位:鳥よけマット・人工芝(“座れない面”を作る)
なぜ効く?
室外機の上・手すり天面などの休憩スポットを“座りにくい質感”にして、居心地を下げる。
向いている環境
・室外機上にフン跡/手すりの同じ地点に汚れが集中
設置のコツ
- 面で敷き詰め、隙間ゼロ(端から端まで)
- 両面テープや面ファスナーで着脱式にして掃除しやすく
よくある失敗
- 島状に小さく置く→その縁に着地される/風でズレる
維持の目安
- 月1で位置と固定の再確認/汚れた面は洗って乾燥
第4位:反射テープ・モビール(視覚で“落ち着かない”)
なぜ効く?
光のチラつき+動きで「ここは安心できない」と感じさせる。初動の牽制に有効。
向いている環境
・下見段階の来訪/被害がまだ軽度/賃貸で置くだけ・吊るすだけから始めたい
設置のコツ
- 高さと長さを変えて複数/風で必ず揺れる位置
- 2週間ごとに位置替え(慣れ対策)
よくある失敗
- 1〜2本だけで“無視”される/動かない位置に吊るして静止物化
維持の目安
- 月1で配置替え/色あせたら交換
第5位:忌避ジェル・顆粒・スプレー(匂い・感覚で“いやな場所”)
なぜ効く?
におい・ベタつきで着地ラインを不快に。他の対策の補助として効果的。
向いている環境
・手すりのエッジや室外機の縁など“線”を狙われる場所
設置のコツ
- 点在配置で“安全地帯”を作らない
- 雨・直射で効果低下→こまめに補充
よくある失敗
- 1回塗って放置/広範囲にベタ塗りして景観・触れやすさ悪化
維持の目安
- 週1〜2で薄れ確認/雨後に補充
環境・生活スタイル別の最適解
小さなお子さん・ペットがいる
→ ネット or ワイヤー+マット(無臭・触れにくい対策中心)
賃貸・景観を崩したくない
→ ワイヤー2本+控えめモビール(固定はクリップ・結束・面ファスナー)
角部屋・コーナーに集まりやすい
→ ネットで角を“面封鎖”+反射タッセルを角へ
室外機上の滞在が多い
→ マット全面敷き+上方にモビール(吹出口は塞がない)
強風エリア・高層階
→ 物理中心(ネット・マット)/視覚系は固定点多めに
黄金コンボ(長持ちしやすい組み合わせ)
- 本命封鎖:ネット(面)+手すりワイヤー(線)
→ 侵入・着地の両方を同時に遮断 - 静かに目立たず:ワイヤー2本+人工芝マット
→ 景観配慮しつつ“座れない化” - 初動〜軽度:反射テープ複数+手すり縁にジェル点在
→ まずは来訪頻度を落とす
失敗パターンと即リカバリー
- テープだけで運用 → 物理(ワイヤー or マット)を追加
- 一箇所だけ強化 → 動線全体を面で管理(角/手すり全長/室外機)
- 固定が弱い → 風向きを想定して固定点追加+連続固定
- すぐ戻ってくる → 痕跡ゼロ運用(フン・羽毛・小枝は即除去)をセットで
予算×時間の目安(体感ベース)
- 3,000円・半日:ワイヤー2本+マット → 着地阻止が実感しやすい
- 5,000円・1日:角のネット囲い+反射モビール → 巣作り予防に強い
- 8,000円〜・1日:ベランダ全面ネット+補助でテープ → 長期安定
※費用は目安。賃貸は原状回復を最優先に。
すぐ使える選び方チェック
- □ 手すり・室外機・角の着地スポットを特定した
- □ 物理(ネット/ワイヤー/マット)を1つは入れる
- □ 視覚や匂いは補助として重ねる
- □ 固定は連続、隙間ゼロ/避難経路は確保
- □ 2週間ごとの小変更計画を立てた
- □ 痕跡ゼロ習慣(掃除→乾燥→微調整)を回す
まとめ:
「入れない面」+「止まれない線(面)」+「落ち着かない演出」を重ねることで、鳩は“ここは安心できない”と学習し、自然と寄りつかなくなります。まずは今の被害レベルに合わせて物理を1つ導入し、視覚・匂いで慣れ防止を添えるのが、無理なく続けられるコツです。
よくある質問(Q&A)
Q1. 鳩がもうベランダに巣を作ってしまったらどうすればいいですか?
A. 巣ができてしまった場合は、個人で無理に撤去するのはNGです。鳩は法律で保護されている鳥なので、勝手に卵や雛を処分すると違法になることもあります。管理会社や自治体に相談し、専門業者に依頼するのが安心です。
Q2. 忌避スプレーやジェルって、本当に効果がありますか?
A. 単体では鳩が慣れてしまうこともありますが、物理対策(ネットやマット)と併用すると効果的です。スプレーは短期的、ネットは長期的、といった使い分けがおすすめです。
Q3. 100均のグッズだけで十分ですか?
A. 軽度の被害なら十分効果があります。特に「反射テープ」「園芸ネット」「人工芝マット」は人気の定番アイテムです。ただし、被害が深刻な場合はネットや業者対応も検討してください。
Q4. 掃除のときに気をつけることはありますか?
A. はい。乾いたまま掃かないことが大切です。必ず霧吹きなどで湿らせてから拭き取ってください。マスク・手袋をつけ、作業後はしっかり手洗いをすれば安心です。
Q5. マンションでも自由に対策できますか?
A. ベランダの内側なら個人で対策できますが、手すり外側や外壁などの共用部分は管理会社の許可が必要です。まずは写真で被害を記録して、管理会社に相談するとスムーズですよ。
まとめのひとこと
鳩対策は「寄せつけない・居つかせない・戻らせない」が基本。
今日からできる小さな工夫を積み重ねれば、鳩の来ない快適なベランダ生活を取り戻せます。
まとめと今後の対策
ベランダに鳩が来てしまうのは、鳩にとって「安心できる・休める・巣を作れる」と感じる環境があるからです。
しかし、放置してしまうとフンによる汚れや悪臭、洗濯物の被害、さらにはご近所トラブルに発展することもあります。
だからこそ、早めに対策を始めることが一番の近道。
- まずは フンや巣材を残さず掃除して“痕跡ゼロ”に
- 100均アイテム(反射テープや人工芝マットなど)で 今日からできる対策 を
- 被害がひどい場合は ネットやワイヤーなど物理的なバリアを導入して、長期的に安心できる環境をつくりましょう
鳩はとても賢く、一度「ここは居心地が悪い」と学習すれば自然と寄りつかなくなります。
複数の対策を組み合わせて、定期的に見直すことで効果がぐんとアップしますよ。
🌿 安心して洗濯物を干せるベランダ、快適に過ごせる住まいを取り戻すために
今日できる小さな一歩から、ぜひ鳩対策を始めてみてくださいね。







