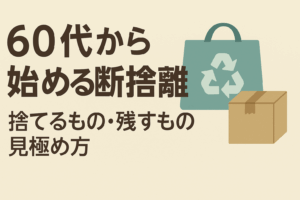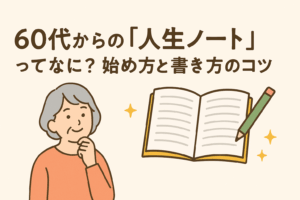60代は、子育てや仕事を一段落し、「自分のための時間」が増える世代。
そんな中で、多くの人が手に取るのが“読書”という趣味です。
本には、人生を見つめ直す力、日々に彩りを与える力があります。
この記事では、60代からの読書習慣におすすめの本をジャンル別に10冊厳選してご紹介します。
読書習慣を持つメリット|60代だからこそ本と向き合う時間を
- 脳の活性化(言葉・記憶・想像力の刺激)
- 気分転換やストレス解消に
- 会話のきっかけや共通の話題ができる
- 人生経験と照らし合わせて、本から得る気づきが深まる

「読書」は時間もお金もかからず、一人時間を豊かにする最高の趣味です!
60代は、人生を振り返りながら、これからの時間をどう過ごすかを考える大切な時期。
そんな日々に寄り添ってくれるのが、本の存在です。
ここでは、心をほぐし、前向きな気持ちになれるおすすめの本をジャンル別に10冊ご紹介します。
60代におすすめ!心が豊かになる本10選【ジャンル別】
60代は、人生を振り返りながら、これからの時間をどう過ごすかを考える大切な時期。
そんな日々に寄り添ってくれるのが、本の存在です。
ここでは、心をほぐし、前向きな気持ちになれるおすすめの本をジャンル別に10冊ご紹介します。
① 『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』人生の深みを味わう小説
著:ブレイディみかこ
イギリスで暮らす著者と、その息子が通う公立中学校での体験を綴った、エッセイ形式のリアルな教育・社会観察記です。
一見軽やかな筆致ながら、テーマはとても深く、
- 貧困と格差
- 多様性とアイデンティティ
- 正義や偏見、社会の不条理
など、現代社会が抱えるリアルな問題が、少年の目線で描かれます。人生の深みを味わう小説
なぜ60代の心に響くのか?
- 子育て経験や家族との関係を振り返りながら、親として・社会の一員としての視点で共感できる
- 若者の視点を通して、これからの時代の価値観や教育のあり方に気づかされる
- 難しいテーマをユーモアと温かさで包んでおり、読みやすく、心にじんわり残る



「息子にどう伝えるか」を考える著者の姿に、親としての“静かな葛藤”や“優しさ”を重ねる方も多いです。
シニア世代にとっては、「次世代とどう向き合うか」を考えるヒントにもなります。
②『日日是好日(にちにちこれこうじつ)』エッセイ・随筆で心をほぐす
著:森下典子
「日日是好日」とは、禅語で「毎日が良き日」
良い日・悪い日ではなく、“今日”そのものを大切に生きようという意味が込められています。
このエッセイでは、著者が20年以上にわたり続けてきた茶道の学びを通して、
季節のうつろい、所作の美しさ、人との関わり方、そして人生の深みを、やさしい言葉で丁寧に綴っています。
なぜ60代におすすめなのか?
- 人生において「続けること」「変わっていくこと」の両方を自然に受け入れる感覚が描かれている
- 小さな変化(季節、音、香り、空気)に心を開くことの尊さを再確認できる
- 何かを新しく始めたいと思っている人にも、“遅くない“始めるのに理由はいらない”と背中を押してくれる



60代は「自分の時間をどう使うか」を見直す時期。
この本は、日常にある“静かな幸せ”を見つけるレンズを与えてくれます。
『日日是好日』は、派手ではないけれど、読むたびに心の奥にしみ込んでくる“人生の教科書”のような一冊です。
③『わたしのウチには、なんにもない。』シンプルライフ・暮らしの本
著:ゆるりまい
「物を減らすことで、暮らしも心も整う」をテーマに、徹底した“片づけ”と“手放す”ことの哲学を、コミックエッセイ形式で描いたベストセラーです。
主人公の「まいさん」は、かつては物をため込みがちだったのに、ある日を境に大転換。
自分の心に素直になっていくうちに、「必要なものしか持たない=心がラクになる」というライフスタイルにたどりつきます。
なぜ60代の暮らしにおすすめなのか?
- これからの暮らしを“身軽で快適”にしたいと考える世代にぴったり
- 家の中を見直すことで、生活全体にリズムが生まれる
- 「いつか使うかも」という気持ちとどう向き合うか、心の整理にもつながる
- 「減らす=失う」ではなく、「残すもの」を選ぶという前向きな行動になる



“片づけ”は作業ではなく、「暮らしをととのえる入り口」。
『わたしのウチには、なんにもない。』は、そんな気づきを軽やかに与えてくれる一冊です。
④『置かれた場所で咲きなさい』心が軽くなる生き方の本
著:渡辺和子
カトリック修道女であり、教育者でもあった著者・渡辺和子さんが、人生における“逆境”や“心の持ちよう”を、あたたかな言葉で綴ったベストセラーエッセイ集です。
タイトルの「置かれた場所で咲きなさい」には、
“与えられた環境を嘆くのではなく、今いる場所で精いっぱい生きる”という深い意味が込められています。
60代にとって、なぜ心に響くのか?
- 「思うように動けない日」「孤独を感じる時間」が増えてくる中、“今ある場所”の大切さに気づかせてくれる
- 長年頑張ってきたからこそ、「もう無理しなくていい」と優しく肯定してくれる言葉に出会える
- 「人生の秋」をどう味わい、どう受け止めるか、そんな静かな問いに応えてくれる



『置かれた場所で咲きなさい』は、誰の人生にもある“立ち止まる時間”に、そっと寄り添ってくれるやさしい本です。
人生のリズムが変わってくる60代にこそ、ぜひ手に取ってほしい一冊です。
⑤『老いの才覚』シニア世代向けの短編集
著:曽野綾子(作家・カトリック信徒)
“老い”を悲観せず、堂々と受け止めながら、自立した生き方を選ぶことの大切さを、歯切れよく綴ったベストセラー随筆です。
60代におすすめする理由
- 「老い」の入り口に立つ60代にとって、“これからの生き方”を考えるきっかけになる
- 誰もが避けて通れないテーマに、前向きで現実的な視点を与えてくれる
- 価値観が多様化する時代に、“人にどう見られるか”よりも“どうありたいか”を教えてくれる



「若さを保つ」より、「老いを楽しむ」視点に気づかされます。
⑥『ひとりをたのしむ』自然や暮らしと向き合う随筆
著:群ようこ(作家・エッセイスト)
「ひとりの時間」が寂しさではなく、“大人の自由”や“心地よさ”に変わっていく感覚を、軽やかな筆致で綴ったエッセイ集です。
著者の日常や考え方を通して、
- 人とつながらなくても満たされる
- 無理に人付き合いをしなくていい
- 「ひとりでいること」を自分らしく楽しむコツ
が、ユーモラスに、そしてさりげなく語られます。
なぜ60代に響くのか?
- 退職・子どもの独立・配偶者との死別など、“ひとり”になるタイミングが増える世代
- 他人の目を気にせず、“好きなことを好きなようにやる”ことの心地よさを再確認できる
- 孤独を受け入れるのではなく、“楽しみに変える力”をくれる



『ひとりをたのしむ』は、静かな日常の中にある幸せを見つける本です。
60代からのひとり時間を、もっと自由に、もっとやさしく過ごしていきたい方に、ぴったりの一冊です。
⑦『銀の匙(ぎんのさじ)』昔読んだ名作を“再読”して味わう
著:中勘助(なか かんすけ)/1910年発表・自伝的小説
『銀の匙』は、明治時代末〜大正初期の日本を背景に、ひとりの少年が見た「幼年期の記憶」や「日常の美しさ」を、静かで繊細な文体で描いた作品です。
物語の舞台は祖母の家。
草花の匂い、陽だまり、家族の声、食卓の記憶……。
ごく日常的な情景が、詩のような美しい日本語で丁寧に綴られており、「読むだけで懐かしさに包まれる」と語られる名作です。
なぜ60代からの「再読」におすすめなのか?
- 若い頃には気づけなかった“何気ない日々の価値”に気づける
- 過ぎ去った時間を優しく思い返す「読書による回想体験」になる
- 今の時代には失われつつある慎ましさ・季節感・人との距離感が心に響く
- 自身の「原風景」や「家族の思い出」がよみがえるような感覚に



読み終わったとき、人生の“静かな美しさ”が心に残る──そんな余韻が魅力です。
『銀の匙』は、派手さはなくても、一冊で“人生の豊かさ”をしみじみと感じさせてくれる文学作品です。
⑧『嫌われる勇気』哲学・考え方の本(読みやすい入門編)
著:岸見一郎・古賀史健
(2013年出版・アドラー心理学をベースとした対話形式の自己啓発書)
どんな本?
- 哲人(哲学者)と青年の対話形式で進む、「自分らしく生きる」ための心理学的な教え
- アルフレッド・アドラー(心理学の三大巨頭の一人)の考えを、わかりやすい会話スタイルで現代に落とし込んだ一冊です
- 「トラウマは存在しない」「すべての悩みは対人関係」など、一見過激に見える主張の中に、深い納得と解放感があります
なぜ60代におすすめなのか?
- 「自分のために生きる」という視点が強く求められる世代
→ 仕事や子育てなど“誰かのため”に生きてきた時間を経て、「自分はどうしたいのか」と問う時期にぴったり - 人間関係のストレスや葛藤に悩まされてきた人にとって、“他人の期待に応えなくてもいい”というメッセージは大きな救い
- 家族・親戚・ご近所との距離感に悩む場面で、「課題の分離」の考えが役立つ



“嫌われる勇気”とは、わがままになることではなく、自分の人生に責任を持ち、自分らしく生きる選択をする勇気。
『嫌われる勇気』は、60代からの人生を「自分の手に取り戻す」ための知恵がつまった一冊です。
⑨『70歳が老化の分かれ道』健康・体と心のケア本
著:和田秀樹(精神科医・高齢者医療の専門家)
この本は、「老化は“年齢”より“習慣と心がけ”で決まる」という視点から、
70歳を過ぎてからの人生を“老け込まず、明るく、前向きに生きる”ための実践アドバイスをまとめた実用書です。
60代が読むべき理由とは?
- 「70歳になってからの差」は、60代の過ごし方で決まる
- 「まだ元気なうちに」できる対策・習慣が多数紹介されている
- 体力や気力の下降を「自然なこと」とあきらめず、自分で意識的に食い止める方法が学べる



『70歳が老化の分かれ道』は、ただの健康本ではありません。
60代の今こそ、「これからの自分の人生を、自分で選んでいく」という気づきをくれる、“行動につながる1冊”です。
最近の著書『老いたら好きに生きる』良かったです。
⑩『60歳からの趣味入門』趣味を広げる実用本
編:成美堂出版編集部
この本は、60代以降の“セカンドライフ”を楽しく充実させるための趣味ガイドブックです。
手軽に始められるものから、生きがいや仲間づくりにつながるものまで、幅広いジャンルの趣味を紹介している実用的な1冊です。
本の特徴・内容ポイント
- 「やってみたいけど、自分に合うかわからない…」という人でも安心のやさしい導入解説
- 趣味をジャンルごとに分類して、実践の仕方・楽しみ方・費用感・必要な道具などをわかりやすく紹介
- 写真や図解が多く、パラパラと眺めるだけでもワクワクできる
なぜ60代にぴったりの一冊なのか?
- 定年退職や子育て終了後の「ぽっかり空いた時間」を充実させたい人に最適
- 体力や関心に合わせて、無理なく“自分に合った趣味”を探せる
- 初心者向けで、「始め方」や「失敗しないコツ」が丁寧に紹介されている
- 仲間と楽しむ趣味も多く紹介 → 人とのつながりのきっかけづくりにも◎



「今から始めても遅くない」──そう思わせてくれる、背中をやさしく押してくれる本です。
まとめ|読書は「60代からの人生を豊かにする栄養」
60代は、仕事や子育てなど「誰かのために使っていた時間」が、少しずつ“自分のための時間”に変わる時期です。
その時間をどう使うかで、人生後半の充実度は大きく変わります。
そして「読書」は、特別な道具や環境がいらないのに、
心に栄養を与え、想像力を育て、人生を深く味わわせてくれる最高の“ひとり時間の相棒”になります。
なぜ“今”読書が心に響くのか?
- 若い頃に読んだ本を今読むと、全く違う感想になる
- 人生経験を重ねたからこそ、物語の裏にある“人の感情”や“生き方”に深く共感できる
- 文章の美しさ、静かな語り、余白のある表現が、心にじんわりと沁みてくる



「ただ知識を得るため」ではなく、「心を育てるため」の読書に変わっていくのが、60代からの読書の魅力です。
読書は“脳と心の運動”にもなる
- 集中力を保つ → 認知機能の維持に◎
- ことばを覚える・思い出す → 脳の活性化
- 感情の揺れを言葉に置きかえる → ストレス緩和・癒し効果
- 笑ったり、泣いたり、想像したりする時間 → 「感じる力」を取り戻す
そして何より、自分を肯定できるようになる
- 本の登場人物に共感し、「自分もこんな気持ちになったことがある」と思える
- 迷っている自分に、「そのままでいいよ」と言ってくれる言葉に出会える
- 日常を丁寧に生きる大切さ、“人生に遅すぎることなんてない”という希望が生まれる
60代からの読書は、“心の旅”でもあり、“自分と向き合う時間”でもある
- 忙しかった日々では気づけなかったことに、そっと気づかせてくれる
- 読むほどに、自分の考え方や気持ちが整ってくる
- 静かな夜やひとり時間が、人生の“ご褒美”のように感じられるようになる
まずは、気になった一冊から始めてみませんか?
難しい本でなくても、短いエッセイでもかまいません。
「なんとなく気になる」「読んでみたい」──
その直感から生まれる一冊との出会いが、人生に彩りを添えてくれます。



読書は、静かだけれど確かに、人生を豊かにする“心のごちそう”。
あなたの“これから”の時間を、もっとやさしく、もっと楽しくしてくれます。